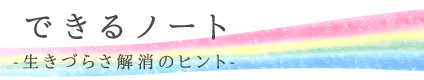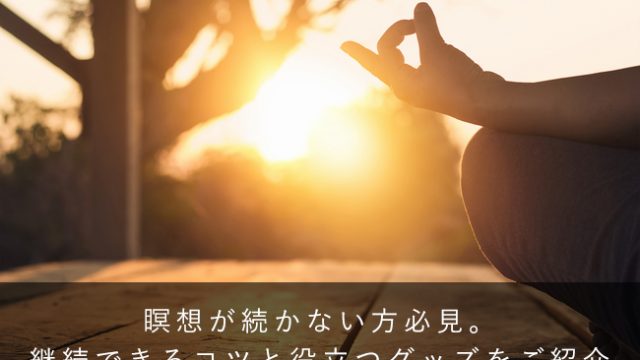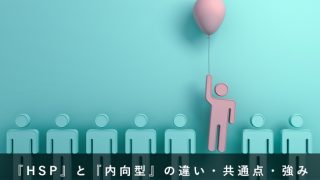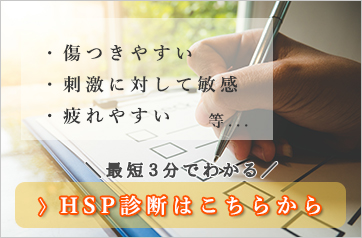「集団の中にいるのが苦手」「細かい情報を感知しすぎる」「大きな音や声に過剰反応してしまう」
このようなことで「疲れ」を感じやすいのが、“HSP”と呼ばれる敏感・繊細な気質の方です。
HSP気質の方は、人の気持ちを読み取ったり共感する能力にも長けています。そのため、他人の感情や考えに振り回されやすいといった特徴もあり、それも「疲れやすさ」を感じる要因の一つとなっています。
私自身、内向的な性格、そしてHSP気質ということもあり、人混みなどの刺激の強い場所で長時間過ごすとグッタリと疲れてしまうことが多くありました。
こうしたエネルギーの消耗を少しでも防ぐために、様々な対策を考え、実践してきた結果、今では日常生活において強い疲労感を感じることはほとんどなく、心穏やかに過ごせる時間を大幅に増やすことができました。
今回は、私が実際に試してきて特に高い効果を感じることができた「疲労の予防と対策法」を6つご紹介したいと思います。
この記事の目次
疲れやすさの原因『敏感・繊細』はどこからくる?

そもそも、疲れやすさの原因にもなっている「敏感さ」や「繊細さ」はどこからくるものなのでしょうか?
実は、HSPの特徴である敏感さ・繊細さは“生まれつきの特徴”だと考えられています。
人それぞれ身長や骨格に違いがあるのと同じように、この敏感さや繊細さも、その人を形成する特徴のひとつなのです。
ただ、育った環境や、健康状態によってもそうした気質が助長されるケースもあります。
親に十分な愛情を与えてもらえなかった場合(アダルトチルドレン)
例えば、親に適切なサポートを受けられずに育ったような場合は、人の感情に敏感になりやすく、周りの反応が過剰に気になったりすることがあります(アダルトチルドレンと呼ばれます)。
こうした方は、「愛情不足」や「厳しすぎる教育」、「人と比べられて育った」などといったことが原因で、自分も他人も信頼できず、不安や恐怖といった感情を抱きやすくなってしまうことがあるのです。
親は子どもに対して心から愛情を与えているつもりでも、スキンシップが不十分であったり、条件付きで愛情を与えてしまったような場合には、子どもは愛情に対して飢えていきます。
そうした結果、子供は「親の機嫌を取るため」、「親の意識をこちらに向けるため」「親から褒められるため」に行動しようとします。
大人になっても常に周囲の反応をうかがうようになり、それが敏感性を助長する要因となるのです。
たとえば、他人が目の前でイライラしていたり怒ったりしているとそれに同調してしまい、同じように気分が悪くなったり、悩んでしまったりします。
また、他人からの評価や称賛を欲しがることで、誘いや頼まれごとが断りにくかったり、自分の意見をはっきりと言うのが苦手になってしまうこともあります。
自律神経が乱れている場合
HSPの「敏感さ」や「繊細さ」が助長される要因には、『自律神経の乱れ』も関係することがあります。
「自律神経」には、交感神経と副交感神経があります。
交感神経は興奮や行動をつかさどる神経で、反対に副交感神経は休息やリラックス時に働く神経です。
精神が安定しているときは、この2つの神経のバランスも均衡がとれている状態になります。
しかし、ストレスを強く感じたり長期的なストレスを受けることで、交感神経側に強く傾いてしまうことがあります。これが『自律神経が乱れた状態』です。
この状態によって、情緒不安定や神経過敏を引き起こし、「敏感さ」や「繊細さ」を助長する可能性があると考えることができます。
HSP気質の人が疲れやすい場面
- 光やニオイ、音などの刺激が多いとき
- 人前に立って話をするとき(注目を浴びる)
- 集団の中にいるとき
- 威圧的な人、攻撃的な人が近くにいるとき
- 一度にたくさんのことをやらなければいけないとき
- 突発的な出来事や変化に対応しなければいけないとき
- 精神的なプレッシャーがかかる仕事をするとき
- 自分の怒りが爆発してしまったとき(溜め込みやすい分、鎮めるのにも時間がかかりやすい)
上記のように、HSP気質の方は日常生活において疲れを感じるシチュエーションがたくさんあります。
何の対策もせずに過ごしていると、知らず知らずのうちに疲れやストレスを抱え込んでしまう恐れがありますので、あらかじめ何らかの対策をしておくことが大切です。

HSP気質の疲れやすさを未然に防ぐ6つの対策
HSP気質の疲れやすさは、主に周囲に対するセンサーが過剰に働きすぎてしまうことが原因になっています。
そのため、このセンサーに触れるような刺激からできるだけ身を守ることが、疲れやすさを予防するための有効な手立てとなります。
刺激の感じ方は人によって異なり、またそれを和らげるための方法もたくさんありますが、ここでは私自身が効果的だと感じた予防法をいくつかご紹介したいと思います。
HSPの疲れ対策①徹底された事前準備で不安を排除する

HSPの人の中には、豊かな想像力を持つ人が多いといわれています。
「先のことを想像しすぎて不安を感じてしまう」といったことはないでしょうか? 私はよくあります。
いわゆる“取り越し苦労”をしてしまうことが多く、グルグルと同じようなことを考え続けることで疲労を感じることも多いです。
こうした未来への不安を排除するために、私は『徹底的な準備』をすることを心がけています。
悪い結果を想像して「どうしよう」と思い悩むのではなく、「どうしたらうまくいくだろう?」と、成功に近づくための方法を考え、先に万全の対策を打っておくのです。
そうすることで、余計な心配をしたり、ただ漠然と不安を抱え続けることがなくなり、精神的な負担をかなり軽減できるようになりました。

HSPの疲れ対策②心の境界線をイメージする

他人の感情を敏感に察知しやすいのが、HSP気質の代表的な特徴です。
私も、周りにイライラしている人がいるだけでビクビクしたり不安を感じてしまうことがよくありました。
そうして人の感情や場の空気感に影響されることで、知らず知らずのうちに疲労やストレスはどんどん蓄積されていきます。
この問題を未然に防ぐために、私は『心の境界線』を常に意識するようにしています。
心の境界線とは、相手と自分をきっちり区別するためのラインのことで、お互いの責任や問題をごちゃまぜにしないためには必要不可欠な考え方です。
この考え方を知っておくことで、空気を読みすぎたり、他人に同調しすぎることを防ぐことができます。
具体的なやり方については、以下の記事を参考にしてみてください。

HSPの疲れ対策③疲れが溜まっているときには情報を制限する

感受性が豊かなHSP気質は、見聞きすることに対して過剰反応してしまうことがあります。
例えばSNSやニュースサイトなどを通じて刺激の強い情報に触れるにつれ、マイナスのエネルギーを吸収してしまったり、体力を消耗してしまうこともあります。
とくに疲れが溜まっているときは、それを弾き飛ばすようなエネルギーが不足しやすくなりますので、注意が必要です。
そんなときには、私は以下のような方法でエネルギーの消耗を防ぐようにしています。
- 休憩中にスマホを手にとるのをやめ、ただ目を閉じる
- オフライン時間を増やす(ネットに極力接続しない)
- アプリの通知をオフにする
- 完全に一人になれる時間を増やす
- 自然に触れる時間を増やす
- 寝る前にスマホを見ない
こうした方法を通じて刺激を減らすことも、疲労を予防するためには大切なことだと思います。

HSPの疲れ対策④苦手な場所はアイテムで自分の世界を守る

ガヤガヤと騒がしい場所、ニオイや光が気になる場所など、自分が苦手だと感じるようなシーンでは、できるだけ自分の世界を守るためのグッズを使い疲労やストレスを軽減することが大切です。
私は以下のようなグッズを上手く活用し、外部からの刺激を極力少なくするようにしています。
- 耳栓
- サングラス
- マスク
- アロマ
- ブルートゥースイヤホン
注意したいことは、あまり依存しすぎないこと。あくまでもストレス軽減のために使用することを目的とし、極端に頼りすぎないことが大切です。
また、耳栓やイヤホンで音を防ぎすぎると思わぬ事故に遭遇してしまう可能性もありますので、周囲の音が適度に聞こえるくらいに調節することも大切なポイントです。

HSPの疲れ対策⑤呼吸法で緊張を鎮める

バリアを十分に張り切れなかった結果、周囲から不快な刺激を受けてしまうことで、感情が高ぶったり落ち込んだりしてしまうことがあります。
このとき、自律神経は興奮や緊張をつかさどる交感神経が優位になっており、一度切り替わるとなかなかリラックス状態にもっていくことができません。
自律神経は人の意思ではコントロールできない器官ですが、唯一「呼吸」によってある程度の調整が可能になります。
スポーツの世界でも、本番で冷静さを保ち実力を発揮するために様々な呼吸法を用いますが、これは高ぶった神経を素早く鎮める効果が期待できるためです。
呼吸法による自律神経の調整方法にはいくつか種類が存在しますが、「腹式呼吸」が最も簡単に取り入れやすいものです。
たとえば、
- 大きな音や声にビックリしたとき
- 周りに不快な人がいるとき
- 緊張やプレッシャーを感じるとき
このようなときにその場で腹式呼吸をするだけで、自律神経の高ぶりを抑え、気持ちを落ち着かせることができます。
腹式呼吸の簡単なやり方については、以下の記事でご紹介しています。よろしければご参考ください。

HSPの疲れ対策⑥自分が感じた感情を否定せず受け入れる

この方法は、精神的な疲労を軽減するために非常に役立つ考え方です。
HSPで悩みやすい人は、自分の繊細さや敏感さを「自分を苦しめる欠点」のように捉えてしまいがちです。
「なぜ自分だけこんなに弱いんだろう?」「情けない」などと、自分の“弱さ”にだけ意識が向き、自分を責めたり嫌ったりしてしまうことが多いのです。
しかし、こうしたストレスをいつも抱えていると、前述した「交感神経」を刺激し、敏感さに拍車をかけることになりかねません。
そうならないためには、自分が感じたことを否定せず、そのままに受け入れてやることが大切です。
例)「失敗するのではないか?」と不安を感じてしまうとき…
否定する考え方・・・「こんな小さなことでまた不安になってしまった」「どうしてこんなに臆病なんだ」「こんなに弱い自分はダメだ」
受け入れる考え方・・・「不安を感じているんだね」「失敗するのは怖いよね」「そう思うのは仕方のないことだよ」「今はそれでいいんだよ」
自分が感じたことに対して否定する考えが浮かぶ場合、「○○でなければならない」「●●してはいけない」などといった信念が心のどこかに存在しています。
その信念が原因となって強い不足感や自己否定感が生じているような場合は、
「自分は今こんな気持ちを味わっている」
と、自分が感じた気持ちを否定することなく受け入れてあげましょう。
その上で、
- 「そんな風に感じても大丈夫だよ」
- 「そう感じるのは当然のことだよね」
- 「今はそれでいいよ」
などと、“許し”や“励まし”の言葉をかけてあげるのです。
そうすることで、自分が強く気にかけていた気質(敏感さ・繊細さなど)のことが、それほど気にならなくなっていくはずです。
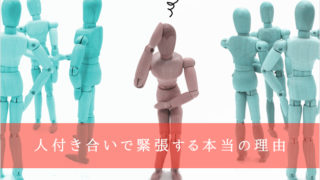

最後に:
以上、疲れやすさの予防法や対策を6つご紹介しました。
周囲に意識が向きやすいHSP気質は、疲労の元となる刺激を人一倍受けてしまいがちです。
しかし、前向きな思考を持ち、自分の性質に合った生活スタイルを模索することで、HSP気質による疲労は確実に減らしていくことができます。
ぜひ今回ご紹介した方法を参考にし、できそうなことから取り組んでみてください。
少しでも良くなることを願っています。

〈まとめ〉
- 繊細敏感な気質は生まれつきの性質
- 幼少期の環境や健康状態でHSP気質が助長されることがある
- ①思い悩むのではなく、事前準備で不安を排除しよう
- ②心の境界線で自分と他人の問題を区別しよう
- ③疲れが溜まっているときは情報を制限しよう
- ④刺激の強い場所はアイテムを活用しよう
- ⑤呼吸法で緊張を和らげよう
- ⑥自分の感情を否定せずに受け入れよう
対人関係において不安や緊張を覚えやすく、実生活で精神的苦痛や疲弊を感じやすい性質や傾向を『シャイネス』といいます。
シャイネスの中には、『内気』や『恥ずかしがり』、『人見知り』といったものも含まれ、それが原因で人付き合いを避けてしまう方は多いとされています。
このオンライン講座では、全14日間のメールレッスン+ワークシートの実践を通して、人に対する緊張や不安を和らげ、安心して人と付き合うための思考法や行動についてお伝えしていきます。
お好きなタイミングでメールを開封していただき、ご自分のペースで実践していただけることが最大のメリットです↓